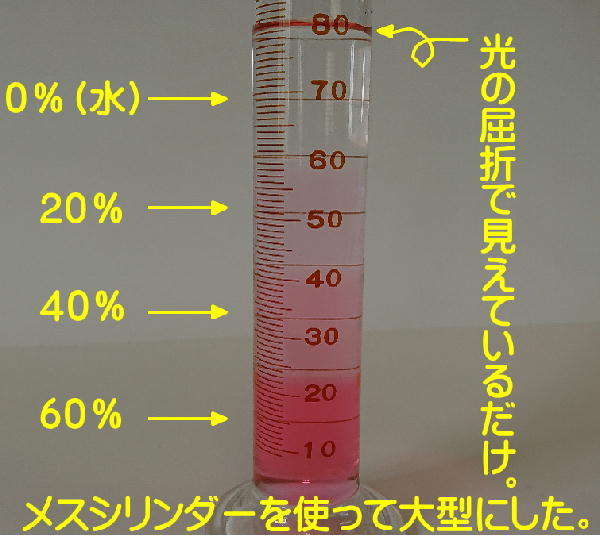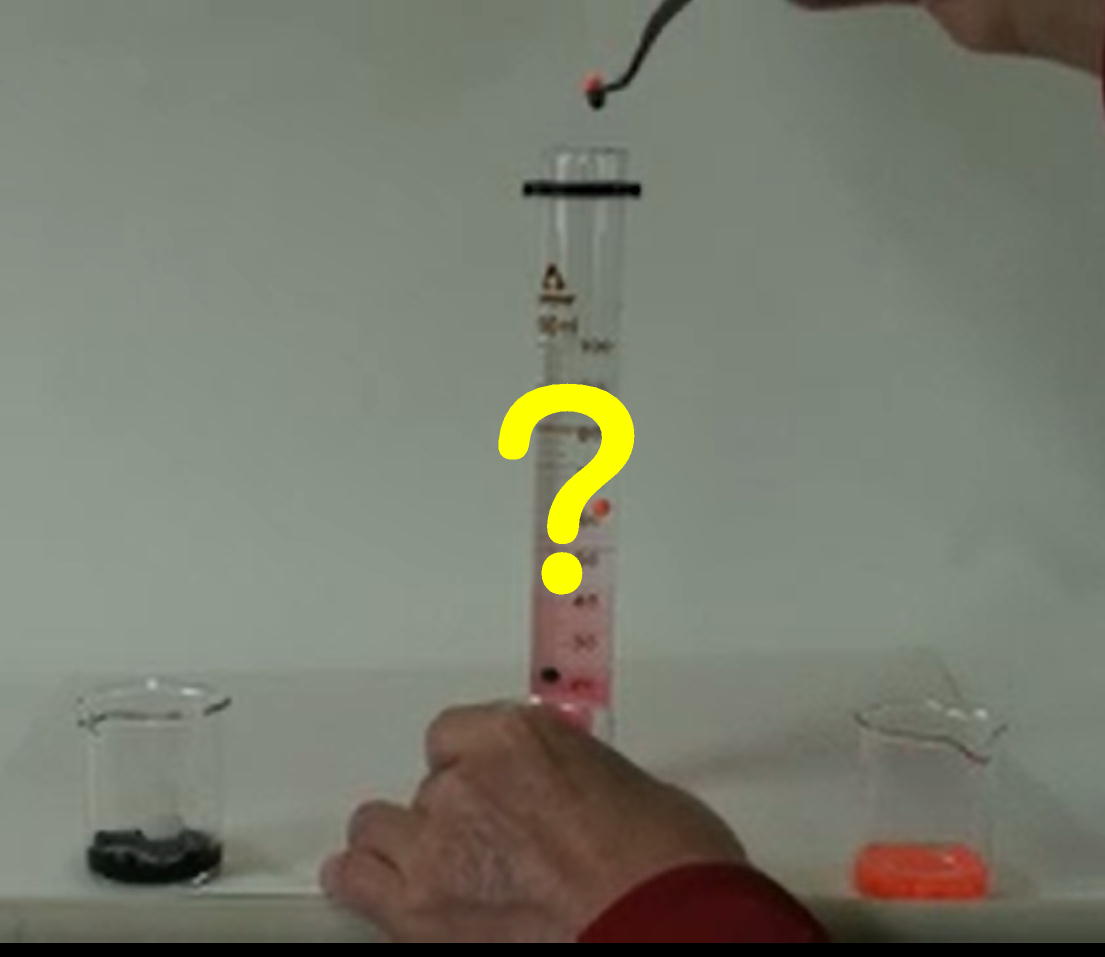全員理系なので大丈夫だとは思いますが、単位体積当たりの質量のことです。
私が小学生の時に、よくやった遊びがあります。
まず「3秒以内に答えなさい。」と言ってから、
「鉄5キロと綿5キロはどっちが重いか?」という質問をします。質問が終わると、「1,2,3」と数え、答えないと「ハイだめー」などと言って冷やかします。
さて、小学生にする質問ですが、答えはわかりますよね。「鉄」…などと考えた人はいないでしょうね。
どちらも「5キロ」なのですから、同じ重さです。
ここで、思わず「鉄」と考えてしまうのは。綿よりも鉄のほうが、同じ体積だったら思いから、つまり密度が大きいからです。
密度が大きい・小さいと、重い・軽いは別のことですが、混同しやすいので気を付けてください。
ヒトの体の密度は、ほとんど水と一緒です。息を思いっきり吸えば水に浮きますし、息を全部吐けば沈みます。
ヒトの体脂肪率によっても密度は異なります。
ボクサーのように筋肉質で体脂肪率の極端に低い人は密度が大きく、水に浮きません。きっと水泳は苦手なはずです。
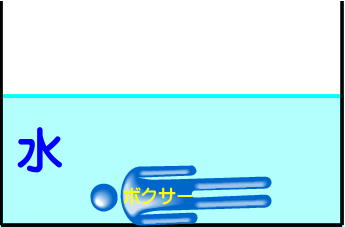
しかし、死海には浮きます。(死海が何かについてはコチラ)

飽和食塩水と真水は、密度が違うので、飽和食塩水の上に、真水を静かに乗せると、しばらくは分離したままです。
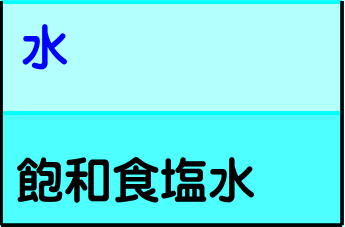
ここに、ボクサーのように体脂肪率が低い人を置いたらどうなるでしょうか。
こんな風に、飽和食塩水よりも上で、真水よりも下の部分に留まります。
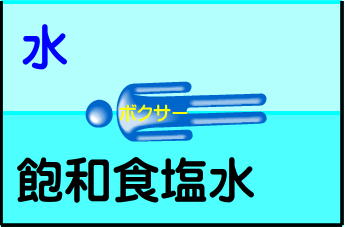
さらに、これを層にしないで、少しずつ変化した食塩の濃度勾配を作ると、人によってとどまる場所が異なる。
逆に、とどまる位置によってその人の密度がわかることになる。
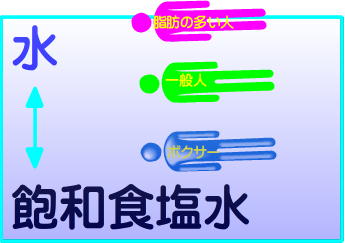
もちろん、この関係は、様々な物質にもあてはまります。
実際の映像を見てみましょう。
食塩水よりも作りやすいショ糖で濃度勾配を作ります。
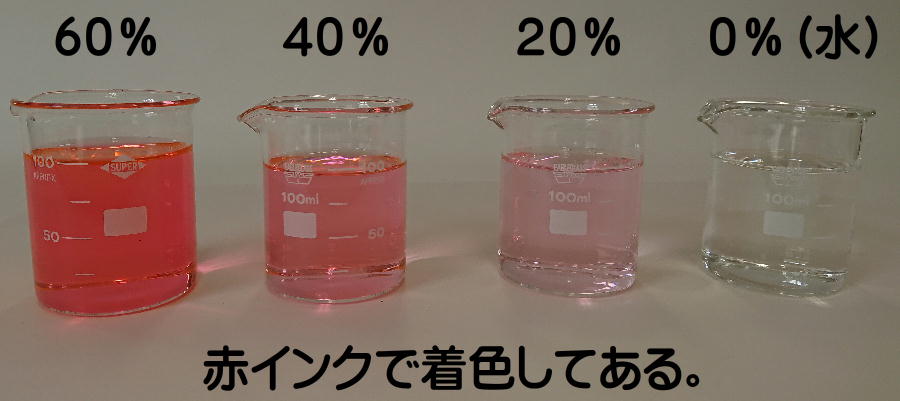
ショ糖液の各濃度の密度は以下の通り。
60% 1.29
40% 1.18
20% 1.08
0%(水) 1.00
層を作ってみましょう。
駒込ピペットで、混ざらないように慎重に入れていきます。
(ちなみにこの人は、森田先生の友人) 写真をクリックすると動画が見られます。
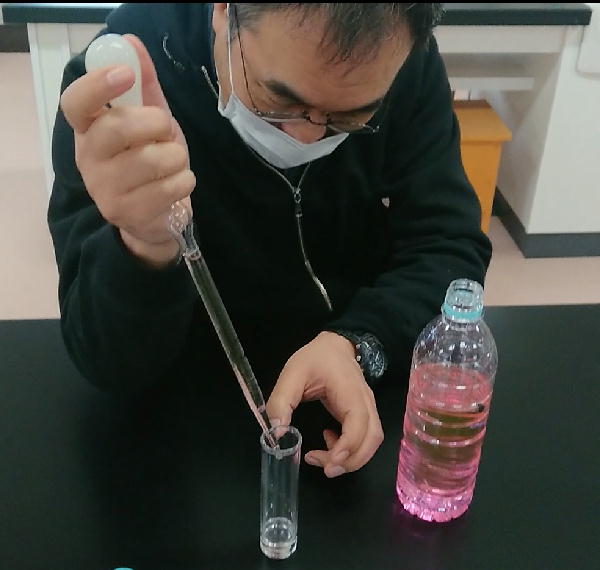
動画